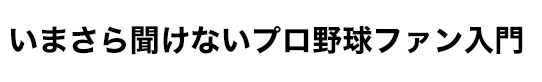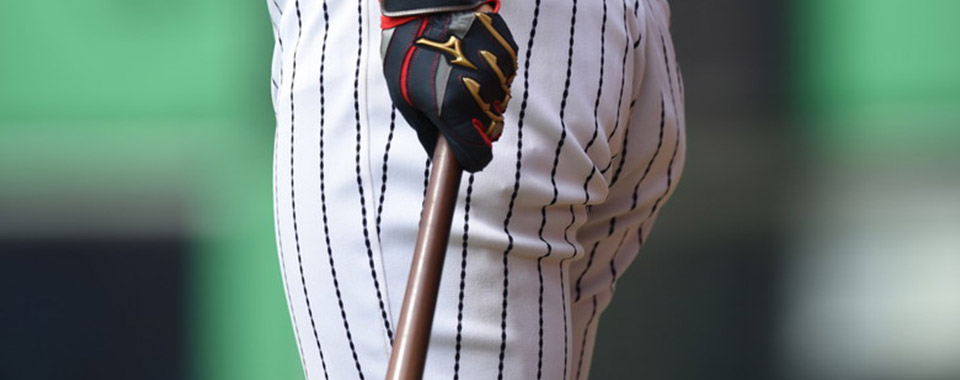
野球用語入門 ゲッツー

野球用語として出てくるゲッツー、アルファベットで表せば、GET TWO になります。直訳すれば、二つ得ることです。何を?アウトをです。主に選手間の口語として使われ始め、今では解説などでも使われるようになりましたが、その意味はほとんどダブルプレーと同じです。
より正確にいえば、一つの守備機会で二つのアウトを得ることになります。守備機会とは、ボールインプレイ(ボールが生きている)の状態中に打者、打者走者、走者に対して守備側が対応することですが、ゲッツーとは一つの守備機会の中で二つのアウトを取ることを言います。
具体例を挙げれば、ランナー一塁で打者がゴロを打ち、二塁手が補球したボールを二塁ベースカバーに入っていた遊撃手に送球して走者が二塁ホースアウト、続いて遊撃手がゴールを一塁へ転送、一塁手が捕って打者走者がホースアウトになる場合などがあげられます。野球では比較的よく表れる守備行為です。
あくまでも口語としてできた言葉ですので、正確な定義はというといささか曖昧ですが、客観的な表現としてのダブルプレーを、守備側の主観的な表現としてあらわした言葉と考えることができます。野球用語としては入門段階の言葉ですので、気楽に考えて大体の感じで理解しておけばいいでしょう。

野球の入門編 タッチアップ

野球の入門編として挙げられる知識には様々な物がありますが、今回はタッチアップについて説明をしたいと思います。テレビで野球中継を見ていると、タッチアップの場面をよく見ることができるでしょう。野球の基本的なルールとして、打者がフライを打った際ランナーは帰塁しなければなりません。帰塁しないと、元々いたベースにボールを送られてアウトになります。これは、野球をかじったことがある人であれば誰もが知っている基本的なルールです。タッチアップは、ランナーが帰塁している状態から走り出すことで、フライが野手に捕球されたと同時に塁から離れることが出来ます。
つまり、よくテレビ中継で見るのは大きな外野フライで三塁ランナーが生還する場面ですが、可能であれば他の塁でも先の塁へフライの捕球と同時に向かうことが出来るというルールです。ランナーの速さ、外野手の肩の強さによっても左右されますが、大きなポール際へのライトフライであれば、二塁ランナーが三塁へ行くことも十分に可能であると言えるでしょう。また、未経験者で誤解している方もたまにいますが、ファウルフライでも走ることができますので覚えておきましょう。
外野手のファインプレーでフェンス際でファウルフライをスライディングキャッチするような姿もよく見かけますが、ノーアウト、もしくはワンアウトの場面それを見たランナーに走られることもあります。

プロ野球 ブックメーカー
ブックメーカーは、18世紀の後半にイギリスで発祥したスポーツの勝敗で、現在ではヨーロッパだけで100万人以上の人が利用しています。
その具体的な内容は、スポーツのオッズを提示して予想投票を募集し、的中した人に配当を行うというものです。
イギリスなどでは既に50年以上前に政府から公式に承認されており、アンダーグラウンドではびこるカルチャーではないという点が明確に違っています。
ブックメーカーが人気を集めているのは、このようにオープンであるということだけが理由ではありません。ブックメーカーは日本のプロ野球やアメリカのメジャーリーグ(MLB)などプロスポーツをはじめとして、WBCやオリンピックやワールドカップなどの幅広くスポーツのオッズを提供しています。
日本のプロ野球は多くのブックメーカーがユーザーに対してオッズを提供していて、公式戦すべての試合で勝敗予想をすることが可能になっています。
試合の勝敗予想だけではなく、優勝予想やMVPの予想などオッズは盛りだくさんです。メジャーリーグの方が、オッズの種類は多いです。